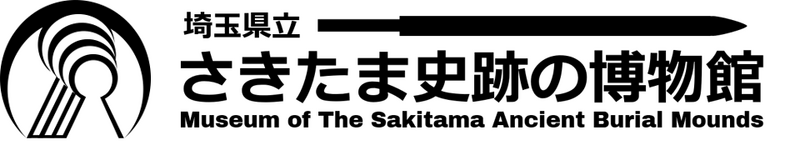休館中ブログ「いまなにしてる?」の更新は、今回が最後になります。
約7カ月間、長いようで短い間でした。
たくさん見ていただき、ありがとうございました!
今後、当館は次のメディアにより情報を発信していきます。
① 公式X
@sakitama_museum
当館の最新情報や、埼玉古墳群や博物館の豆知識、イベント実施の様子などを発信します。
「鉄剣エピソードゼロ」「古代人の日常」「博物館のおしごと」のような、シリーズ企画も行われることがあります。 Xのアカウントをお持ちの方限定になりますが、当館のファンなら必ずフォローしてみてください。
② 公式LINE(4月中旬から配信開始予定)
当館で今後行われるイベントや展示について、最新情報を配信します。
スマートフォンの「LINE」まで通知をお届けできるので、イベント開催を見逃したくない方にお勧めです!
4月には、次のページから友だち追加ができるようになります。
https://sakitama-muse.spec.ed.jp/official_line
③当HP
「新着情報」では、新しい展示の開始や他館との連携企画についてお知らせします。
「イベント情報」では、当館が開催...
いよいよ、再開館まであと1週間となりました。
今回は、リニューアルした「さきたま体験工房」を特集いたします!
今回は、3月3日(日)に行われた「あおぞら まが玉教室」と「キッズ古墳群ガイドツアー」のようすをお伝えします。
あおぞら まが玉教室
当館で常時開催していた「まが玉づくり体験」は休館に伴い休止中のため、まが玉を屋外で作れるイベントを開催しました。会場は さきたま古墳公園の駐車場からほど近い、「北側レストハウス」でした。
どうも、古代人です。
この前、博物館の人から面白そうな企画を聞いたから紹介するよ!
企画名は「『ニュー咲きほこれ埼玉』みんなで踊ろう!埼玉愛を届けよう」。埼玉を愛する人たちから短い動画を募集しているみたい。
2024年2月3日(土)に愛宕山古墳の現地見学会を開催しました。
数日前には雪が降ってしまいましたが、当日は晴天に恵まれ、計401名の方にご参加いただきました。多くのご参加ありがとうございました!
学芸員からは、調査の成果として、①周堀(内堀・外堀)を確認できたこと ②前方部で旧表土(古墳時代の地表面)及び中断テラスが確認できたこと ③前方部の墳丘の始まりや墳裾部を確認できたことを中心にお話ししました。
また、見学会では普段登ることのできない墳丘に登っていただくこともメインのひとつでした。普段と違った景色で古墳をご覧いただけたのではないかと思います。
見学会の様子1
当館は、小・中学生を対象にした全3回の継続型イベント「学芸員の仕事にチャレンジ!」を開催してきました。
今年度の初回は「古墳を歩いて大きさを測ってみよう」、第2回は「出土物を観察スケッチしよう」、
まとめとなる3回目は、「古墳の調査をしてみよう」と題して、愛宕山古墳の発掘体験を行いました。
本物の古墳を発掘できるなんて、なかなかできないスペシャルな体験です。
愛宕山古墳の発掘体験
愛宕山古墳の発掘現場で学芸員が説明を行っているところ。
学芸員から発掘の仕方について説明を受けたあと、いよいよ発掘体験の開始です。
土が固くて掘るのは大変ですが、みんな夢中で掘り続けています。
2月5日午後から翌6日未明にかけて、さきたま古墳公園のある行田市にもかなりの雪が降りました。
6日午前中までの積雪量は10センチ程度でした。
雪を被った古墳もなかなか映えています.。
どうも、古代人です。
また博物館の出張授業をお手伝いしたので、そのときのことを書きます!
(前回のお手伝い記事→ 小学校向け「古墳時代へタイムスリップ!」)
今回の出張授業は「オリジナル埴輪を作ろう!」。埴輪(はにわ)の作り方を勉強して、実際に作ってみる授業だよ。
小学生の高学年からが多いけど、特別支援学校(学級)や中学生のみんなもやっている大人気プログラムなんだって。
授業のようす。
今年も新年早々、発掘調査が始まっています。
今回の調査は墳丘南側(前方部側)の周堀と墳丘北側(後円部側)の墳裾の範囲を確認することが目的ですが、墳丘南側の周堀はほぼ調査が完了しました。
重機で掘削した後、遺構面を確認するために移植ゴテ(=園芸などで使用する小さなスコップ)、ガリ(または三角など呼び方は様々あります)、鋤簾(ジョレン)などの道具を駆使してきれいにしていきます。
(精査作業の様子)
すると...
休館中でもグッズがほしい という方必見!
実は休館中でも当館のグッズは郵送によってご購入いただけるんです。(代金先払い。お届けは、代金お支払から2週間程度要します。)
どれもオリジナルで人気なものばかりですが、今回はその中でも、特に売れ筋なものを紹介いたします。
①トートバック白・黒
1月12日より、来年度ボランティアの募集が始まりました。
募集するのは、環境整備ボランティア30名程度、学習支援ボランティア若干名です。
学習支援ボランティアの活動内容は以前にも紹介したので、
今回は環境整備ボランティアの活動について紹介していきます。
活動日時は、毎週火曜日9:00~11:00です。原則、月2回程度の参加をお願いしています。
主な内容は ①園内の除草・清掃、②花の植え替え・手入れ です。
①園内の除草・清掃
環境整備ボランティアの皆さんには、お花のあるところを中心に、除草をしたり落ち葉を集めたりしていただいています。
さきたま古墳公園は39.6万㎡の広さがあり、これは東京ディズニーランドより少し小さいくらいなので、きれいに保つのは大変です。もちろん清掃会社の方にも日々の清掃をお願いしていますが、ボランティアの皆さんのお力があるとたいへん助かります。
新レストハウス前花壇除草の様子
どうも、古代人です。
歴史と民俗の博物館の特別展「縄文コードをひもとく」に行ってきた記録、最終回です!
第1回 第2回
展示室の最後は「最後の縄文土器」。縁のあたりに「浮線網状文」(ふせんあみじょうもん)という細い網模様がついていることが多いんだって。
水鳥形埴輪の3Dモデルを公開しました。
公開ページ(外部サイトへ移動します。)
今回3Dモデル化した館蔵資料は、瓦塚古墳から出土した水鳥形埴輪です。この水鳥形埴輪は、平成2年度に実施された瓦塚古墳の発掘調査で前方部西側の外堀から出土し、その出土状況から本来は中堤に並べられていたものと推測されています。この資料は足ひれがあることから水鳥であるとされており、白っぽい粘土が塗ってある可能性があることから白鳥を模したものかもしれません。
瓦塚古墳ではこれ以外にも多くの形象埴輪が出土しており、それらの出土状況からどのような配列で形象埴輪が並べられていたのかを復元し、形象埴輪を古墳に並べることの意味を考える研究も行われています。
今後とも少しずつではありますが、瓦塚古墳の形象埴輪をご紹介していきたいと考えています。
(史跡整備担当)
↓ 3Dモデルを見てみる
どうも、古代人です。
前回 に引き続き、歴史と民俗の博物館で開催中の特別展「縄文コードをひもとく」に行ってきた話をするよ。
第Ⅱ部で最初に見たのは、蛇の頭がついた土器だよ。縄文時代の人は、蛇を何か大切なものとみなしていたみたいだね。1個だけじゃなく、ほかにも蛇らしき装飾がついたものがあったよ。
イノシシ、鳥など他の動物が表現されたものもあったけど、面白かったのはこの小さな器。横から見ると、カエルがお風呂に入っているように見えるよ。
どうも、古代人です。
今、「埼玉県立歴史と民俗の博物館」で、縄文時代の土器を特集する展示が開催されているのを知っていますか?
その名も、「縄文コードをひもとく 埼玉の縄文土器とその世界」。
この前チラシを見て気になったので、実際に展示を見てきました! 今回はそのときのことを振り返るよ。
博物館の公式X(旧Twitter)にも写真を投稿しているから、アカウントのある方はぜひ見てね。
11月18日(土)にシンポジウム『6世紀の東国史と埼玉二子山古墳-最新成果から描く継体朝前後の東日本-』が行田市教育文化センター「みらい」にて開催されました。
当日は314名の方にご来場いただき、大盛況のうちに終了しました。たくさんのご来場、誠にありがとうございました!
今回のシンポジウムは、武蔵国で最大規模の前方後円墳である埼玉二子山古墳の報告書刊行を記念して発案されました。
コーディネートは、二子山古墳の発掘調査をはじめ埼玉古墳群の保存整備のご指導をいただいている、明治大学文学部教授の若狭徹先生にお務めいただきました。
若狭先生 開催趣旨説明
先月、埼玉県博物館連絡協議会東・北部地域連絡協議会主催による研修会が開催されました。
「埼玉県博物館連絡協議会」とは、会員相互の交流と連携を目的に、県内81か所(令和5年度現在)の博物館関連施設が加盟する団体で、現在県内4つの地域協議会(南部、西部、東・北部、秩父)に分かれてそれぞれが活動を行っています。さきたま史跡の博物館が所属する東・北部地域連絡協議会(24か所が所属)では、例年夏から秋にかけてスタンプラリー事業、秋に研修会を行っています。
今年度の秋の研修会は、宮代町にある日本工業大学工業技術博物館を会場に行われました。
展示見学の様子。
令和5年9月1日から始まりました改修工事期間中の展示室の様子をご紹介します。
こちらは休館前の国宝展示室と企画展示室の様子です。
休館中は展示室内も工事を実施するため、展示ケース内の埴輪等を取り出し、ケース内を空にしました。
「バーチャル埼玉」は、今年の県民の日(11月14日)に立ち上がった新しいWebサイトです。
スマートフォンやパソコンから、3次元空間に入って埼玉県の魅力を体験することができます。
バーチャル埼玉 入場直後の画面。
中央に表示されているのは、アバター(操作するためのキャラクター)です。タッチや右のボタンクリックで操作できます。
バーチャル埼玉内はいくつかのエリアに分かれており、空中歩行やクイズに挑戦などもできるようです。今回はその中から、当館も出展している「蔵造りブース」をご紹介します。
11月1日から愛宕山古墳の発掘調査がはじまりました。
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、愛宕山古墳は埼玉古墳群の中で最小の前方後円墳で、墳丘全長が54.7mです。同じく埼玉古墳群の中にある二子山古墳は武蔵国で最大の前方後円墳で、墳丘全長が132.2mもあります。比べてみるとその差がよくわかります。
昭和56年に埼玉県教育委員会と行田市教育委員会によって2回調査が行われており、前方部南側調査区の東南部では内堀のコーナー部が確認されています。
下記URLより報告書をご覧いただけますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。
1985_埼玉古墳群発掘調査報告書第三集_愛宕山古墳_埼玉県教育委員会.pdf
{{item.Topic.display_summary}}