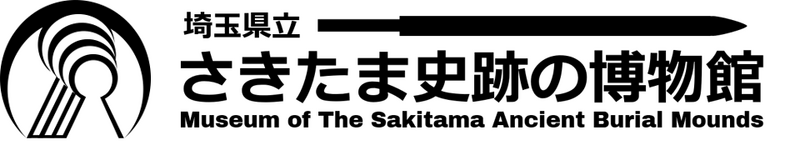休館中ブログ「いまなにしてる?」の更新は、今回が最後になります。
約7カ月間、長いようで短い間でした。
たくさん見ていただき、ありがとうございました!
今後、当館は次のメディアにより情報を発信していきます。
① 公式X
@sakitama_museum
当館の最新情報や、埼玉古墳群や博物館の豆知識、イベント実施の様子などを発信します。
「鉄剣エピソードゼロ」「古代人の日常」「博物館のおしごと」のような、シリーズ企画も行われることがあります。 Xのアカウントをお持ちの方限定になりますが、当館のファンなら必ずフォローしてみてください。
② 公式LINE(4月中旬から配信開始予定)
当館で今後行われるイベントや展示について、最新情報を配信します。
スマートフォンの「LINE」まで通知をお届けできるので、イベント開催を見逃したくない方にお勧めです!
4月には、次のページから友だち追加ができるようになります。
https://sakitama-muse.spec.ed.jp/official_line
③当HP
「新着情報」では、新しい展示の開始や他館との連携企画についてお知らせします。
「イベント情報」では、当館が開催...
いよいよ、再開館まであと1週間となりました。
今回は、リニューアルした「さきたま体験工房」を特集いたします!
今回は、3月3日(日)に行われた「あおぞら まが玉教室」と「キッズ古墳群ガイドツアー」のようすをお伝えします。
あおぞら まが玉教室
当館で常時開催していた「まが玉づくり体験」は休館に伴い休止中のため、まが玉を屋外で作れるイベントを開催しました。会場は さきたま古墳公園の駐車場からほど近い、「北側レストハウス」でした。
どうも、古代人です。
この前、博物館の人から面白そうな企画を聞いたから紹介するよ!
企画名は「『ニュー咲きほこれ埼玉』みんなで踊ろう!埼玉愛を届けよう」。埼玉を愛する人たちから短い動画を募集しているみたい。
2024年2月3日(土)に愛宕山古墳の現地見学会を開催しました。
数日前には雪が降ってしまいましたが、当日は晴天に恵まれ、計401名の方にご参加いただきました。多くのご参加ありがとうございました!
学芸員からは、調査の成果として、①周堀(内堀・外堀)を確認できたこと ②前方部で旧表土(古墳時代の地表面)及び中断テラスが確認できたこと ③前方部の墳丘の始まりや墳裾部を確認できたことを中心にお話ししました。
また、見学会では普段登ることのできない墳丘に登っていただくこともメインのひとつでした。普段と違った景色で古墳をご覧いただけたのではないかと思います。
見学会の様子1
当館は、小・中学生を対象にした全3回の継続型イベント「学芸員の仕事にチャレンジ!」を開催してきました。
今年度の初回は「古墳を歩いて大きさを測ってみよう」、第2回は「出土物を観察スケッチしよう」、
まとめとなる3回目は、「古墳の調査をしてみよう」と題して、愛宕山古墳の発掘体験を行いました。
本物の古墳を発掘できるなんて、なかなかできないスペシャルな体験です。
愛宕山古墳の発掘体験
愛宕山古墳の発掘現場で学芸員が説明を行っているところ。
学芸員から発掘の仕方について説明を受けたあと、いよいよ発掘体験の開始です。
土が固くて掘るのは大変ですが、みんな夢中で掘り続けています。
2月5日午後から翌6日未明にかけて、さきたま古墳公園のある行田市にもかなりの雪が降りました。
6日午前中までの積雪量は10センチ程度でした。
雪を被った古墳もなかなか映えています.。
どうも、古代人です。
また博物館の出張授業をお手伝いしたので、そのときのことを書きます!
(前回のお手伝い記事→ 小学校向け「古墳時代へタイムスリップ!」)
今回の出張授業は「オリジナル埴輪を作ろう!」。埴輪(はにわ)の作り方を勉強して、実際に作ってみる授業だよ。
小学生の高学年からが多いけど、特別支援学校(学級)や中学生のみんなもやっている大人気プログラムなんだって。
授業のようす。
今年も新年早々、発掘調査が始まっています。
今回の調査は墳丘南側(前方部側)の周堀と墳丘北側(後円部側)の墳裾の範囲を確認することが目的ですが、墳丘南側の周堀はほぼ調査が完了しました。
重機で掘削した後、遺構面を確認するために移植ゴテ(=園芸などで使用する小さなスコップ)、ガリ(または三角など呼び方は様々あります)、鋤簾(ジョレン)などの道具を駆使してきれいにしていきます。
(精査作業の様子)
すると...
休館中でもグッズがほしい という方必見!
実は休館中でも当館のグッズは郵送によってご購入いただけるんです。(代金先払い。お届けは、代金お支払から2週間程度要します。)
どれもオリジナルで人気なものばかりですが、今回はその中でも、特に売れ筋なものを紹介いたします。
①トートバック白・黒
1月12日より、来年度ボランティアの募集が始まりました。
募集するのは、環境整備ボランティア30名程度、学習支援ボランティア若干名です。
学習支援ボランティアの活動内容は以前にも紹介したので、
今回は環境整備ボランティアの活動について紹介していきます。
活動日時は、毎週火曜日9:00~11:00です。原則、月2回程度の参加をお願いしています。
主な内容は ①園内の除草・清掃、②花の植え替え・手入れ です。
①園内の除草・清掃
環境整備ボランティアの皆さんには、お花のあるところを中心に、除草をしたり落ち葉を集めたりしていただいています。
さきたま古墳公園は39.6万㎡の広さがあり、これは東京ディズニーランドより少し小さいくらいなので、きれいに保つのは大変です。もちろん清掃会社の方にも日々の清掃をお願いしていますが、ボランティアの皆さんのお力があるとたいへん助かります。
新レストハウス前花壇除草の様子
どうも、古代人です。
歴史と民俗の博物館の特別展「縄文コードをひもとく」に行ってきた記録、最終回です!
第1回 第2回
展示室の最後は「最後の縄文土器」。縁のあたりに「浮線網状文」(ふせんあみじょうもん)という細い網模様がついていることが多いんだって。
水鳥形埴輪の3Dモデルを公開しました。
公開ページ(外部サイトへ移動します。)
今回3Dモデル化した館蔵資料は、瓦塚古墳から出土した水鳥形埴輪です。この水鳥形埴輪は、平成2年度に実施された瓦塚古墳の発掘調査で前方部西側の外堀から出土し、その出土状況から本来は中堤に並べられていたものと推測されています。この資料は足ひれがあることから水鳥であるとされており、白っぽい粘土が塗ってある可能性があることから白鳥を模したものかもしれません。
瓦塚古墳ではこれ以外にも多くの形象埴輪が出土しており、それらの出土状況からどのような配列で形象埴輪が並べられていたのかを復元し、形象埴輪を古墳に並べることの意味を考える研究も行われています。
今後とも少しずつではありますが、瓦塚古墳の形象埴輪をご紹介していきたいと考えています。
(史跡整備担当)
↓ 3Dモデルを見てみる
どうも、古代人です。
前回 に引き続き、歴史と民俗の博物館で開催中の特別展「縄文コードをひもとく」に行ってきた話をするよ。
第Ⅱ部で最初に見たのは、蛇の頭がついた土器だよ。縄文時代の人は、蛇を何か大切なものとみなしていたみたいだね。1個だけじゃなく、ほかにも蛇らしき装飾がついたものがあったよ。
イノシシ、鳥など他の動物が表現されたものもあったけど、面白かったのはこの小さな器。横から見ると、カエルがお風呂に入っているように見えるよ。
どうも、古代人です。
今、「埼玉県立歴史と民俗の博物館」で、縄文時代の土器を特集する展示が開催されているのを知っていますか?
その名も、「縄文コードをひもとく 埼玉の縄文土器とその世界」。
この前チラシを見て気になったので、実際に展示を見てきました! 今回はそのときのことを振り返るよ。
博物館の公式X(旧Twitter)にも写真を投稿しているから、アカウントのある方はぜひ見てね。
11月18日(土)にシンポジウム『6世紀の東国史と埼玉二子山古墳-最新成果から描く継体朝前後の東日本-』が行田市教育文化センター「みらい」にて開催されました。
当日は314名の方にご来場いただき、大盛況のうちに終了しました。たくさんのご来場、誠にありがとうございました!
今回のシンポジウムは、武蔵国で最大規模の前方後円墳である埼玉二子山古墳の報告書刊行を記念して発案されました。
コーディネートは、二子山古墳の発掘調査をはじめ埼玉古墳群の保存整備のご指導をいただいている、明治大学文学部教授の若狭徹先生にお務めいただきました。
若狭先生 開催趣旨説明
先月、埼玉県博物館連絡協議会東・北部地域連絡協議会主催による研修会が開催されました。
「埼玉県博物館連絡協議会」とは、会員相互の交流と連携を目的に、県内81か所(令和5年度現在)の博物館関連施設が加盟する団体で、現在県内4つの地域協議会(南部、西部、東・北部、秩父)に分かれてそれぞれが活動を行っています。さきたま史跡の博物館が所属する東・北部地域連絡協議会(24か所が所属)では、例年夏から秋にかけてスタンプラリー事業、秋に研修会を行っています。
今年度の秋の研修会は、宮代町にある日本工業大学工業技術博物館を会場に行われました。
展示見学の様子。
令和5年9月1日から始まりました改修工事期間中の展示室の様子をご紹介します。
こちらは休館前の国宝展示室と企画展示室の様子です。
休館中は展示室内も工事を実施するため、展示ケース内の埴輪等を取り出し、ケース内を空にしました。
「バーチャル埼玉」は、今年の県民の日(11月14日)に立ち上がった新しいWebサイトです。
スマートフォンやパソコンから、3次元空間に入って埼玉県の魅力を体験することができます。
バーチャル埼玉 入場直後の画面。
中央に表示されているのは、アバター(操作するためのキャラクター)です。タッチや右のボタンクリックで操作できます。
バーチャル埼玉内はいくつかのエリアに分かれており、空中歩行やクイズに挑戦などもできるようです。今回はその中から、当館も出展している「蔵造りブース」をご紹介します。
11月1日から愛宕山古墳の発掘調査がはじまりました。
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、愛宕山古墳は埼玉古墳群の中で最小の前方後円墳で、墳丘全長が54.7mです。同じく埼玉古墳群の中にある二子山古墳は武蔵国で最大の前方後円墳で、墳丘全長が132.2mもあります。比べてみるとその差がよくわかります。
昭和56年に埼玉県教育委員会と行田市教育委員会によって2回調査が行われており、前方部南側調査区の東南部では内堀のコーナー部が確認されています。
下記URLより報告書をご覧いただけますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。
1985_埼玉古墳群発掘調査報告書第三集_愛宕山古墳_埼玉県教育委員会.pdf
土器の3Dモデルを公開しました。
土師器 高坏(鉄砲山古墳出土) by さきたま史跡の博物館【公式】 Sakitama Museum on Sketchfab
https://sketchfab.com/3d-models/13216ee5c2bd4b59814f2c25362d724a
今回3Dモデル化した館蔵資料は、鉄砲山古墳から出土した長脚高坏(土師器)です。この長脚高坏は平成23年度の発掘調査で横穴式石室の正面の墳丘下段テラスから7個体出土しており、埋葬に際して行われた祭祀に関わるものと考えられています。大きさは口縁部径が25㎝ほどで、器高は25~27㎝前後となり、同時期の一般的な集落で出土するものと比較しても大型のものであり、古墳への埋葬祭祀を目的として製作された特殊なものと考えられています。関東地方では、甲塚古墳(栃木県下野市)や金鈴塚古墳(千葉県木更津市)などで出土しており、各地の有力古墳からの出土例が確認されています。
3Dモデルを通して、古墳の埋葬祭祀に使われたと考えられる土器を観察してみてください。
当館の人気体験プログラム、「まが玉づくり体験」。
現在は工事休館中のため、まが玉体験も休止していますが、おうちでまが玉づくりができる「まが玉づくりセット」を郵送で販売中です。
セットの説明書または公式YouTubeチャンネルから、まが玉の作り方の解説動画を見ることができます。
「三▷」(再生リスト)を押すと各動画を切り替えることができます。
この動画は令和2年度に撮影されたものです。しかし、ぼやけたところが多かったり、細かいやり方が説明書と違っていたりします。
(12月7日、新しい動画を公開しました。↑の動画も新しいものに差し替えています。)
そのため、今回の休館中に改めて動画を撮影しました。
博物館本館は現在休館中ですが、「呼んで学ぶ」を実現するため、学習支援担当は様々な学校に出張授業を実施しています。今回は県内の特別支援学校での実践をご紹介します。
今回、出張授業を行ったのは県内の特別支援学校高等部1年生30名。古代人も一緒に授業に参加してくれました。
授業のようす。自己紹介する古代人。
前半は、「古墳時代へタイムスリップ」です。これは、「古墳時代がどんな時代なのか」、「埼玉古墳群ってどんな場所なのか」、「はにわって何か」など古代についての学習を行います。ただ難しい話を一方的に聞いていてもつまらないので、説明の中にはたくさんのクイズが出てきます。そのクイズの回答をグループで考え、ホワイトボードに書いていきます。時には大人でも難しいような問題を、友達と協力して回答を導き出していました。正解したグループには大きな拍手が送られていました。
先週はイベントが連続して、にぎやかな週末でした。
今回は、3(金・祝)と4(土)に行われた「あおぞら まが玉教室」、4(土)の「古墳群ガイドツアー『万葉歌碑をめぐる』」のようすをお伝えします。
あおぞら まが玉教室
さきたま古墳公園の駐車場からほど近い、「新レストハウス」で行われたこのイベント。
さきたま史跡の博物館本館で常時開催していた「まが玉づくり体験」が現在はお休みなので、その代わりという意味合いもありました。
また、埼玉県では11月1日~7日を「彩の国教育週間」と定めています。期間中は、学校・家庭・地域が一体となって、教育に対する関心と理解を一層深める取組を実施しています。
今回のイベントが、ご家庭で同じ体験をたのしみ、様々に言葉を交わすきっかけになっていたら幸いです。
どうも、古代人です。
先日、博物館の出張授業をお手伝いしたので、そのときのことを書きます!
今回の出張授業は「古墳時代へタイムスリップ!」。小学4年生の皆さんに、古墳時代と埴輪、埼玉古墳群について、興味をもってもらうために行いました。
どうも、古代人です。
職員の方のお手伝いで、埼玉県立さきたま史跡の博物館や埼玉古墳群に行った時のことを振り返っているよ。
前回の記事はこちら。
2022年の冬頃に、古墳群を見て回ったんだった(#古代人の日常_Season2)。
南側の古墳を見て、前玉神社に寄ったあと、なにをしたかというと……
いよいよ本日から発掘調査が始まります!
今回は、発掘調査を開始する前の準備の様子をお届けします。
発掘は事前の準備がとても大切で、計画を入れると数年前から決まっていることもあります。
今年度の発掘についても、どこを・どのような目的で・どのように掘るのかを検討してきました。もちろんこれは学芸員だけでなく、大学の先生方や有識者の方々にご指導いただいています。
そして、発掘で使用する機材や重機の契約も大切なお仕事です。つまり、発掘に至るまでには事務業務も多々あります。
こちらは、機材置き場と休憩所の設営風景です。
休憩所設営
新しい埴輪の3Dモデルを公開しました。
Sketchfabで見る(外部サイトが開きます)
今回3Dモデル化した館蔵資料は、将軍山古墳から出土した円筒埴輪です。この円筒埴輪は、平成5年度の発掘調査の際に後円部北側の内堀から出土したものです。ほぼ完形品で、器高は62㎝の4条突帯をもち、色調は橙色で直立状の形状をもつのが特徴になります。
どうも、古代人です。
さきたま史跡の博物館のホームページをご覧の皆様、はじめまして。
わたしは埼玉古墳群とさきたま史跡の博物館に定期的に行っていました。最近、博物館本館が工事休館になって残念に思っていたら、職員の方から、博物館の休館中ブログで記事を書いてくれないかと頼まれて、今書いてます。
職員の人とちがってあまり専門的なことは書けないけど、ファンの一人として、どんなことが楽しかったか思い出しながら書いていくよ。面白そうだなと思ったら、皆さんも行ってみてね。
11月から愛宕山古墳の範囲確認と保存状況を確認するための発掘調査を行います。
今回は令和3年度から2年ぶりの発掘調査で、これまで未調査だった前方部南側及び周堀南側(かつてお店があった場所)が対象です。
調査に当たっては近隣や公園利用者に配慮し、安全に作業を進めてまいります。
なお、発掘調査現場内は大変危険ですので、立ち入りはご遠慮ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
1.調査期間 令和5年11月1日(水)~令和6年2月29日(木)
2.調査地点 愛宕山古墳
3.調査日時 各週の火・水・金曜日の9:00~16:00まで (調査の進捗や天候状況により、変更することがあります)
どんな発見があるか私たちも楽しみです!
休館中ブログにて調査の様子をお伝えしていく予定ですので、引き続きよろしくお願いします。
(史跡整備担当)
現場に関するお問合せ埼玉県立さきたま史跡の博物館 史跡整備担当TEL 048‐559‐1181
当館は、今年10月で開館から54年目を迎えました。
当館が埼玉県立の「さきたま資料館」として開館したのは昭和44(1969)年10月でした。その後、平成18年に「さきたま史跡の博物館」と名前を変え、現在に至ります。
今回の記事では、さきたま資料館開館当時の写真を見てみたいと思います。まずは建物の外観です。
さきたま古墳公園内では様々な花を見ることができますが、
二子山古墳と将軍山古墳の間には、約2,000㎡のコスモス畑が広がっています。
さきたま史跡の博物館は9月1日より改修工事に伴い休館となっておりますが、
改修工事中の当館の状況についてお知らせいたします。
①博物館外のケヤキ並木
博物館へと続くケヤキ並木から博物館までは、安全のためのフェンスで囲われています。
来園者用の通路を確保してありますが、通常時と比べとても狭くなっておりますので、通行には充分お気を付けください。
先日、博物館の近隣の中学校に出張して授業を行いました。 テーマは「郷土の誇り 埼玉古墳群」。古墳群や出土品についてのより深い知識や、地域の人々が古くから地元の古墳に向き合い、保護を行ってきた歴史をお伝えしました。
各地の古墳は、様々な事情で墳丘の部分がなくなってしまったものが多くあります。埼玉古墳群の古墳は今でこそ特別史跡の指定を受け大切にされていますが、かつては消滅が危ぶまれた時期もありました。
残暑が続いた9月も終わり、だいぶ過ごしやすい時期になってきましたね。
さきたま古墳公園内の石田堤付近をお散歩していたところ
おや、何か白いものが見えますね、、、
おやおや?もしかして???
普段は、まが玉づくり体験など各種体験のお手伝いをしていただいている学習支援ボランティアの皆さん。休館中でイベントが限定されている今は、どんなことをされているのでしょうか。
一つは、イベントのための道具の準備です。
火おこし体験で使う道具を作っているところです。これは舞ぎり式というやり方に対応した道具で、板状の部分を上下させると、芯が回って木どうしで摩擦を起こすことができます。
摩擦で熱を持った火種から、火をおこすことになります。
当館の公式YouTubeチャンネルでは、古墳群や展示資料に関する動画を公開しています。
チャンネル内でもっとも多く再生されているのが「さきたま空中ガイドツアー『VR埼玉古墳群』」(令和3年公開)です。
これは、埼玉古墳群の全9基の古墳を上空から見ることができる動画です。指でスワイプしたり、マウスでドラッグすることで視界を360度動かすことができます。
休館中でも図録やグッズがほしい という方 必見!
実は休館中でも当館のグッズは郵送によって御購入いただけるんです。
どれもオリジナルで人気なものばかりですが、今回はその中でもR5.9月現在、特に売れ筋なものを紹介いたします。
①クリアファイル(鉄剣)
当館で展示している「国宝 金錯銘鉄剣」の銘文をあしらったcoolなデザインのクリアファイルです。
写真だと伝わりにくいですが、銘文が透明なため、中に入れる紙の色次第で銘文の色が変わるのが面白いですね。
②埼玉古墳群ガイドブック
全ページフルカラーで印刷された本書を読めば、埼玉古墳群のことはばっちり!A5(?)サイズで持ち運びしやすいのも嬉しいですね。
現在は博物館本館には入れませんが、さきたま古墳公園や将軍山古墳展示館はご利用いただけます。この本と一緒に埼玉古墳群の散策はいかかでしょうか。
③令和5年度図録「二子山古墳と祈りの器」
休館直前まで開催していた企画展の図録です。主に当館学芸員が執筆しています。当館の企画展にいらっしゃった方もそうでない方も古墳や出土品について詳しくなって...
今日は広報のお仕事についてお伝えします。
さきたま史跡の博物館は現在、本館が工事休館となっています。
将軍山古墳展示館は平常通り入ることができます。
(将軍山古墳展示館)
これまで本館の中にあったポスターとチラシを将軍山古墳展示館に移すため、掲示用ラックなどの什器ごと車に乗せて運びました。
入口付近の道がせまく、車を入れるのが大変でした……
無事、設置完了しました。今後さきたま古墳公園で行われるイベントの案内チラシや、Webでも受付中の「故郷さきたま写真展」応募用紙などが置いてあります。
過去の企画展リーフレットなど、ここにしか配架しないものもちらほら。
本館が使えない今、チラシやポスターで広報を行うことができる貴重な場なので、うまく活用していきたいです。
(広報・学習支援担当)
今回は、「出張授業」のおしごとについて紹介します。
出張授業とは、博物館に務める職員(主に教員免許のある者)が、小学校などに出張して授業を行うものです。
博物館のお仕事には、館内に展示を行ったり、資料や史跡を適切に管理したりするだけでなく、その価値や存在を外に伝えていくことも含まれます。たとえば埼玉県内だと、出張授業によって「埴輪」やその欠片を始めて触ったり、初めて「まが玉」を作ったりした方もいるのではないでしょうか。
すでにお知らせしているところですが、本日より埼玉県立さきたま史跡の博物館は改修工事のための休館に入ります。休館は令和6年3月31日までの予定です。
この半年間で、空調・照明などを更新し、資料保管や危機管理の面でより安全な環境になります。長くご不便をおかけしますが、今しばらくお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。
さて、博物館が閉まっている間はイベントも少なくなり、お客様と関わる機会もぐっと少なくなります。そうなると、
「博物館の職員って、いま何してるの?」
そんな疑問をもたれるかもしれません。
2020年コロナ禍の臨時休館においてもそうでしたが、休館している間も、博物館の職員には意外とたくさんの仕事があります。このブログでも、休館中の「博物館のおしごと」についてお伝えしていきたいと思います。
他にも、休館中の各種イベントのお知らせ、HPから楽しめるデジタルコンテンツの紹介、博物館や埼玉古墳群についての小話なども公開する予定です。
更新時にはTwitter(X)の当館公式アカウントでお知らせいたしますので、ご確認をお願いします。
(情報発信検討会)
{{item.Topic.display_summary}}